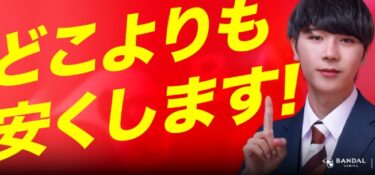2025年10月30日更新

2025年現在の僕の音楽環境です。
こんばんにちは!!
DTMしながら気づいたらハードウェアシンセサイザーを調べまわしている、ぱぴろってぃ(ぱぴ露店店主)です!!

当サイトでは、購入者の目線に立って考えて、厳選した商材を厳選した情報にフォーカスした分析記事を作成しています!!
当記事はシンセサイザーを探している初心者の方向けに、当記事だけで概要を把握して、実際に活用する僕自身の経験からおすすめできる機材を書いていますので、読んでいってくれれば嬉しいです!!
※当記事はリサーチ及びレビューや実体験に基づいた、まとめ記事になります!!
★この記事で解決できる疑問点や判断要素!
- シンセサイザーとは?
- ハードウェアシンセサイザーの選び方!
- 種別別のおすすめなシンセサイザー
★はじめに!

出典:AMAZON
「DTMを始めたいけど、シンセサイザーって何!?」
「プラグインシンセサイザーと何が違うの??」
「演奏もしたい!!」
「一個くらいハードウェアシンセサイザーがあってもいいかなぁ」
「デジタルシンセ?アナログシンセ?リズムマシン?いっぱいあってよくわからん!」
上記のような事を考えて、シンセサイザー、とりわけ「ハードウェアシンセサイザー」について調べていたりしませんか?
僕も最初は同じことを考えていて、一機のワークステーションシンセサイザーを購入しました!(後述するRoland FANTOM)
2024年7月25日更新 出典:AMAZON こんばんにちは!! 夜な夜なチルホップを聴きながら挽きたてコーヒでチルしてる、ぱぴろってぃ(ぱぴ露店店主)です!! ぱぴろってぃ 今回は最[…]

気づいたら様々な機種のハードウェアシンセサイザーを所持し、遊び倒している、現在進行形でほかのハードウェアシンセサイザーを購入しようとしている自分がいます。
どのシンセサイザーでも活用用途が幅広く、メリットも近いですが、当記事ではそれぞれの違い等解説しながら、これ最高!と思えるシンセサイザーをご紹介します!!
なかなか都心部でないと実機も情報も少なくなりがちなシンセサイザーですが、当記事ではできるだけ最初に抑えるべき情報や機材を網羅できているかなと思います!
★シンセサイザーとは!?

出典:AMAZON
シンセサイザーとは、電子回路やプログラムで音を合成し、音楽(楽器の音)や環境音を生み出す機材あるいはプログラムの総称です。
そのなかでさらに以下の様に大別する事が出来ます。
- デジタルシンセサイザー
- アナログシンセサイザー
デジタルシンセサイザーはデジタル信号を用い、アナログシンセサイザーはアナログ信号を用い・・・・という説明は置いておいて、
以下の理解でざっくり把握してる感じになります!!
・デジタルシンセサイザー:基本的にプログラムで構成する音で、プラグインシンセサイザー、一部のハードウェアシンセサイザー
ウェーブテーブルシンセサイザー、FM合成シンセサイザー等多岐にわたる種類がありますが、かなりざっくり言うと、派手で艶やかな音や鋭い音が得意です!
・アナログシンセサイザー:基本的に電子回路と電子部品の発振を利用した楽器で、一部のハードウェアシンセサイザー
どこか暖かみがあり、他のアコースティック(ピアノやエレキギター/ギター等)楽器とも馴染みやすい音色ながら、太く存在感を感じさせる音が得意です!
・バーチャルアナログ/モデリングシンセサイザー:プログラムでアナログの音を再現、または計算して近づけたプラグインシンセサイザー、一部のハードウェアシンセサイザー
上記二つの中間点でいいとこどりともとれる存在です!電子部品の経年劣化みたいな効果も再現しています。
ハードウェアシンセサイザーは実際に機材として物理的に存在する楽器を意味し、プラグインシンセサイザーはPC上で動作するシンセサイザープログラムになります。
当記事ではハードウェアシンセサイザーを扱いますが、これも以下のような種類があります。
- ワークステーションシンセサイザー
- アナログモノフォニックシンセサイザー
- アナログポリフォニックシンセサイザー
- リズムマシン
- セミモジュラーシンセサイザー
- モジュラーシンセサイザー
鍵盤(キーボード)がくっついているものもあれば、シーケンサーと呼ばれる電気信号のみを送り込む機材やMIDI規格の別個体のシンセサイザーやコントローラーが無いと演奏には向かない機材もあったりする電子楽器です。

正直DTM用途を考えると、コストパフォーマンスを考えるとプラグインシンセサイザーが最も優れています。
ただ、ハードウェアシンセサイザーでしか表現できない音色や演奏方法があります。
以下でハードウェアシンセサイザーのメリット・デメリットを解説します。
★ハードウェアシンセサイザーのメリット・デメリット

出典:AMAZON
ここはハードウェアシンセサイザーを弾いたり、自分の楽曲に楽器として音源を使用したりしてハードウェアシンセサイザーを活用する僕自身の偏見が多分に含まれたメリット・デメリットを記載します!
以下の点がメリットと思う所です!
- 自分の音楽活動の相棒として最高に愛着を持った状態で取り組める!
- ハードウェアでしかできない直感的な音の操作!
- 演奏を感性のまま取り組める!
- ハードウェア(アナログ)にしかない音色を用いることができる!
以下に僕自身の動画を掲載しますが、いずれも僕の相棒になっているRoland FANTOM-7 EXを用いた創作物です。
この「相棒感」が僕にとっては特に大切で、モチベーションを極限まで高めてくれていて、「音楽」の中心に常にハードウェアシンセサイザーがいます。(僕がバイカーでもあって、鉄馬の相棒感とほぼ同じなことも影響してるかもです笑)
またツマミを用いた直感的な音の変化、感性によって即時の楽器の切替を行う演奏はハードウェアシンセサイザー独特の強みです!
プラグインシンセシイザーのマウス等操作だと、どうしてもこの部分が実現できないんですよね!
さらにアナログシンセサイザー限定にはなりますが、アナログにしか出ない音色(暖かみ)があったりします。この部分は僕の耳でもなかなか聞き分けられないポイントですが、ほんの些細な音色の違いでヒットするしないも分かれると思うので、音色の選択肢を広げる意味でも有用と思っています。
個人的にはAI全盛期を迎えつつある昨今、実際に演奏したり、直感を磨き貫いた創作の価値がより高まっていくのではないかなと考えています。
以下の点がデメリットと思う所です!
- 高額であることが多い!
- 演奏には練習が必要!
- 場所をとる!
シンセサイザーは立派な楽器なので、値段がそれなりにしますし、低価格なものは露骨に質感や音色がチープだったりします!
フルサイズ88鍵盤のシンセサイザーは大きいので物理的に場所をとります。
(音色はチープさも味なので、これはこれでOKな場合もあります)
DTM用途でのNI社 Kompleteシリーズ等のプラグインシンセサイザーバンドルに比較すると、ある意味ではコストパフォーマンスでは劣っています。(DTMでハードウェアシンセサイザーを使用する場合、”録音”の手間が増えたりもします)
また演奏は、シーケンサーベースのテクノやハウスを除いて、基本ピアノの鍵盤を使用するのですが、一長一短で身につくものでは無く、とにかく練習が必要です。

また僕みたいにハードウェアシンセサイザーの購入欲が増しすぎて沼に陥ることもある意味メリットであり、デメリットですね!(笑)
以下より種類別のシンセサイザーの解説と書くグレード別のおすすめシンセサイザーを記載していきます!
★ワークステーションシンセサイザーについて

出典:AMAZON
ワークステーションシンセサイザーは、メーカー各社(日本限定ですが)の技術を大体全部つぎ込んだ全部入りシンセサイザーになっています。大体どの機種も16個までの楽器を同時にアサインでき、ピアノから弦楽器やドラムキット、シンセサイザーの合成音まであらゆる種類の音色と調整機能が大量に積み込まれています!
これだけでフルオケの作曲が可能なレベルです。※作曲ソフトの方が効率がいいので、作曲のスケッチ兼音源の使い方になると思います。
(最近はPCのDAW〈作曲ソフト〉での作曲が主流なので、ソフト連携も意識されています)
鍵盤がついており、88鍵盤は重さとタッチの繊細さを表現するピアノ鍵盤、それ以下の鍵盤数は弾き心地やあらゆるタッチを実現するシンセサイザー鍵盤が搭載されています。
「全部入り」ではありますが、音源部分はデジタルやデジタルモデリングで、アナログシンセサイザーではありません。
(機種によってはフィルターだけアナログ回路を用いてアナログシンセサイザーの側面を持たせたものもあります)
DTMの用途でも、演奏の用途でもあらゆる音楽用途に向いており、最初の一台として最もすすめできるシンセサイザーです!
一方で機能を積み込みすぎているので、音の調整は機材中央のモニターでPCのような操作を一定程度必要です。
まさしく音楽専用のPC兼とんでも機能満載の電子楽器といった理解でOKです!
★ハイグレードおすすめ:Roland「FANTOM」シリーズ
僕が使用しているモデルで、最強機材です。
何しても、とにかく映える!
特徴としては、アナログフィルター、サンプラー機能、V-PianoというRolandの超高品質ピアノモデリング音源(録音音源ではない)、往年の同社のJupitar-8といった伝説的シンセサイザーをプログラムベースで完全再現したACB技術です。
まんま複数のRolandのシンセサイザーを複数積み込んでいます。各シンセサイザーを0から音作りできたりします!
DAWもCubase、StudioLogic、Ablton Live等との連携で、中央のモニターとスライダーやモニター、サンプラーパッドをDAW操作に用いたりできます!
2025年10月発売のYAMAHAのミドルグレードワークステーションも非常にお勧めです。
RolandよりYAMAHA!な方にもばっちり合うと思います!
★ハイグレードおすすめ:Korg「KRONOS」シリーズ
とにかく玄人受けがすごい当機種。正直できることは上記のFANTOMより多いなと思っています。
特徴は、9つの特徴の違う音源エンジンにより、実質9つのシンセサイザーを搭載している点と、KARMAという自動伴奏提案機能を持っている点。
搭載しているピアノ音源等はどれも高品質で、RolandやYAMAHAが実質DAWと一緒に使用して曲のクオリティを上げていく楽器としてのワークステーションシンセサイザーの方向へ舵を切っている中で、KorgのKRONOSは変わらず単独完結可能なワークステーションシンセサイザーという立ち位置をぶらしていません。
RolandやYAMAHAがLEDで光る機材の方向の中で、これだけLEDが控えめでとにかく渋いです。
ただ中央のモニターが一番渋く、UIがまさしくWindowsみたいな感じで、人を選ぶ機材の側面もありますが、最強性能だと思っています。
★エントリーグレードおすすめ:Roland「Fantom-0」シリーズ/Roland「JUNO-D」シリーズ
上記のFANTOMシリーズの廉価機種ながら、コストパフォーマンスで考えると、ぶっとんで最強機種です。
V-Pianoやn/zyme(ウェーブテーブルシンセサイザー)が削ぎ落されていたり、
本体素材、鍵盤、その他細かな部分が上記FANTOMシリーズより品質が劣るといった廉価特有の特徴こそありますが、逆に買軽く持ち運びできます。(FANTOMは重すぎて無理ですw)
鍵盤もチープというわけではなく、FANTOM程ではないにしろ、ピアノ鍵盤もシンセ鍵盤もきっちり気持ちよく弾けます。
V-Pianoやn/zyme(ウェーブテーブルシンセサイザー)以外のサンプルベース音源やRolandの現在の中心音源Zen-Core等、基本性能は上記FANTOMと同等なので、できることはFANTOMとほぼほぼ変わらないです。
廉価機種とはいってもワークステーションなので、安くはないですが、確実に満足ができる楽器と思います。
さらに予算が限られる場合は、「JUNO-D」シリーズだと購入ハードルがさらに下がります。
Fantom-0シリーズ程の機能は無いながらも、使えるZEN-Core音源が3,800以上あり、持ち運びも容易、電池駆動でDTM以外の用途に大活躍を見込めるだけの機能を備えています。
僕も試奏していていますが、鍵盤のタッチもピアノ鍵盤、シンセ鍵盤共に全くチープ感を感じませんでした!
★おすすめ番外編:Roland「V-stage」シリーズ
こちらはワークステーションでは無いですが、大量の音源を積んだマスターキーボードとしても扱えるステージキーボードになります。
上記のワークステーションとの違いは、作曲関連機能をそいだ代わりに、エフェクト等の操作つまみが前面に出てきている事です。
ワークステーションシンセサイザーよりも直感的に音作りができて、4つとはいえ音源を同時に扱えるので、マスターキーボードとしての使用に向いています。
より演奏向けなので、演奏への意識が高いとより一層向ていると思います。
V-Stageシリーズは、V-Piano(FANTOMより種類が多い)やZen-Core等音源も大量にあり、LEDで明瞭にわかりやすく、かっこよくなっているつまみ類で直感的に操作できるステージキーボードのフラッグシップモデル。
ステージキーボードといえば、以下のNordのStageシリーズですが、昨今の為替円安でより一層高額で手に入りにくい為、ここを意識した製品になっていると思います。
★アナログモノフォニックシンセサイザーについて

出典:AMAZON
アナログモノフォニックシンセサイザーは電子部品が発振し、電子回路によって音色を変えていくアナログシンセサイザーの単音のみ発音できる機材です!
同時に発音できる音数は1音なので、コードの和音は難しいですが、とにかく太く力強い独特な音色を出せるのが最大の強みです。
後述するアナログポリシンセサイザー程高額で、大きいわけではなく、選択肢として入手しやすいのもメリットです。
完全にアナログかつ扱いきれる大きさと機能数であることが多いので、愛着も一層わきやすいです!
※一部セミモジュラーシンセサイザーと被ります。
★ハイグレードおすすめ:MOOG「Subsequent」シリーズ
存在からして「イケてる」再推し機材。
アナログシンセサイザーでは所有者も非常に多いと感じています。
シンセサイザーの生みの親、MOOGのパラフォニックシンセサイザー(同時発音数が2音で、完全なモノシンセではないです)で、MOOG独特の暖かみと野太いサウンドが長所の楽器です。
これは置いておくだけでも、とにかく映える!
現代の機材らしくプリセット(選ぶだけのカスタムされた音色)も豊富にあるので、操作に詳しくなくてもすぐに楽しめます。
音色の特徴から、シンセベースとして愛用されることが多い気がしますが、ウワモノも余裕で行けます!
★ハイグレードおすすめ:MOOG「Messenger」

出典:島村楽器
MOOGの最新のモノフォニックシンセサイザーです。
サウンドハウスや島村楽器等で入手可能です。
伝統の野太さと暖かみを基礎に、ウェーブフォールディング機能や可変ウェーブシェイプ、マルチモード・ラダーフィルターなど、豊かなサウンドの幅を実現する注目の機種。
プリセットが無い、本格派のシンセサイザーですが、上記の「Subsequent」シリーズよりは価格面で優れています。
あまりMOOGはUSB端子を積まないイメージがあるのですが、この機種は積んでいるので、PC等との連携がしやすくなっています!
相変わらずかっこいいです。
★エントリーグレードおすすめ:Beringar「CRAVE」
各社のコピー&機能強化したシンセサイザーを手の取りやすい価格でリリースするBehringarのセミモジュラーモノシンセサイザー。
このCRAVEは鍵盤がついていないタイプですが、下部のシーケンサーゾーンが鍵盤の代替にもなっているので、最低限の音階音色確認が可能です。(MIDIやUSBで鍵盤のあるシンセサイザーやコントローラーとつなげば鍵盤演奏可能です)
3万円ほどのアナログシンセサイザーとしては安価ながら、質感、音が妥協が無いです。
特徴としては、とあるMOOG社の現行機種を意識したと思われる商品構成と音色、名機のアナログシンセサイザー Sequential「Prophet5」でも採用されているVCO(発振電子部品)の採用です。
暖かみのある野太い音とシーケンサーを積んでいるので、フレーズの作曲ができるコスパの神みたい機種です!

廉価機種とはいってもワークステーションなので、安くはないですが、確実に満足ができる楽器と思います。
★アナログポリフォニックシンセサイザーについて

出典:AMAZON
アナログシンセサイザーの複数音の同時発音ができる、アナログシンセサイザーのメインラインナップのジャンルになります!
各社の特徴が色濃く出ており、とにかく豊富な機種が存在します。
コードの和音も含めて複雑な音の動きや鳴りを作り込める電子楽器の究極系と僕は考えています!
単独での演奏はもちろん、DTM等での音源利用としても超強力な戦力になる優れものです!!
★ハイグレードおすすめ:MOOG「MUSE」
僕が最高に憧れているモデルです。
とにかく100点満点のアナログシンセサイザーだと思っています!
特徴としては、8音同時発音可能で、MOOGの伝統のアナログサウンドとわかりやすい各機能の操作つまみのレイアウト、フルサイズのシンセサイザー鍵盤搭載、感性を刺激しまくりな外見です。
正直僕が買うまで売れて欲しくないとまで思っています~今の僕だと置く場所に困りそうですが(笑)
こちらも豊富なプリセットがあるので、買ってすぐに最高のサウンドを楽しめる仕様になっています!
現代機の要、USB端子もきっちり使用可能です。
★ハイグレードおすすめ:Roland「JD-XA」
まさしくRolandらしい外見。
プロ・ミュージシャンから絶大な支持を得ている音源モジュールINTEGRA-7と同じSuperNATURALシンセ・エンジンもアナログ回路とは別で使用可能で、アナログとデジタルのハイブリッドシンセサイザーになっています。
フィルター部分は完全にアナログ回路になっているので、デジタル音源をアナログフィルターを通せることも大きな特徴です。
合計8パート(アナログ4、デジタル4)を同時に発音できるので、ちょっとしたワークステーションシンセみたいな使用方法にも向いています!
アナログポリフォニックシンセサイザーとしては、比較的安価なのも好ポイントです。
少々前のリリースモデルなので、入手できなくなる前に抑えたい逸品です。(廉価機種JD-Xiは新品ではもう入手が難しいです)
★エントリーグレードおすすめ:Korg「VOLCA」シリーズ(VOLKA KEYS)
ここら辺の入手しやすい価格帯のアナログシンセサイザーはKorgの独壇場です。
2万円程でポリフォニックシンセサイザー、されど音は「本物」で、存在感を感じさせてくれます!
VOLKAシリーズはどれも2万円程でFMデジタルシンセサイザー(VOLCA FM2)等いろんなバリエーションがありますが、このVOLCA KEYSは完全アナログポリフォニックシンセサイザーでシーケンサー付き!コスパ、もうすごいです。
鍵盤とは言えないですが、タッチパネル鍵盤で演奏もできます。
同時発音は3音ですが、最低限ともとれる操作ツマミで、初心者向けには抜群に相性が良いです。
USBもプリセットも無い、本格仕様ではありますが、エントリーとしてこれを上回るアナログポリフォニックは無いと思います。
★エントリーグレードおすすめ:Korg「MINILOGUE-XD」
同じくKorgで、上記のVOLKA KEYSよりは価格帯が上がりますが、入手しやすい価格帯の同時発音数4音のアナログポリフォニックシンセサイザーです。
KorgはBehringarと同じく、本体の質感が低価格帯の商品でも良かったりします。このMINILOGUE-XDもメタルボディ、背面ウッドパネルで愛着がわきやすいかっこいい外見になっています。
デジタルシンセサイザーエンジンも搭載しており、ハイブリッドシンセイザーになっています。
音はDTMでも使用がしやすい、使いやすい太すぎず、鋭すぎず、薄すぎない印象。
使い勝手がとにかく良くて、演奏及びDTMで幅広く登場機会がありそうな、八方美人ポリフォニックエントリーグレードシンセサイザーと考えています。

★ミドルグレードおすすめ:Beringar「DeepMind12」
コストパフォーマンスが非常に高い、実用的アナログポリフォニックシンセサイザー。
Rolandの名機「Juno-106」をBeringarの解釈で進化させた、同時発音数12音の優等生な機種だと思います。
「Juno-106」は当時エントリーグレードのアナログポリフォニックシンセサイザーですが、今でもイケてる音が簡単に作れる高い評価を持った機種で、その流れを汲んだ当機種もまたイケてると思います!
「Juno-106」のわかりやすい操作配列をしっかり保持させながら、Beringarの妥協の無い質感の個体と相まって、最高のコストパフォーマンスを感じさせてくれます!
Beringarなので、現代機の要、USB端子も当然使用可能です。
★リズムマシンについて

出典:AMAZON
リズムマシンはドラムキットに特化した操作性とシーケンス構築機能に強みを持つシンセサイザーです!
マシンライブと言われる、シンセサイザーを複数使用した演奏の要だったりします。
ドラムの構成を直感的に操作できる事が最大の長所で、特にキックの音色の存在感はハードウェア特有の音だなと僕は感じています。
バスドラム、スネア、タム、ハイハット等の各種ドラムキットの音を個別にエディット、調整を素早く行えるので、ハードウェアシンセサイザーにはまると必ず一台用意してしまう演奏寄りの機材になります。
DTM用途で考えるとPCではDAW(作曲ソフト)が同機能を担当しているので、リズムマシンに該当するプラグインシンセはありません。ドラムキットの音色のみを搭載したプラグインシンセサイザーを代替として考えます。
リズムマシンの中でも、アナログ、デジタル(サンプルベース)、モデリングと複数の種別のハードウェアシンセサイザーが存在しますが、ここでは一括してリズムマシンとして扱います!
★ハイグレードおすすめ:Roland「TR-8s」/「TR-6s」
Rolandの名機「TR-808」をはじめとしたTRシリーズのモデリング音源を搭載したリズムマシン。
特にTR-8sは「もうこれだけでいいじゃん」ともいえるような操作性と音色と個体サイズを誇ります!
TR-6sはTR-8sの操作端子、同時に重ねられるパート、入出力端子を縮小した廉価グレードですが、使いやすいサイズ感にまとまっており、音自体はTR-8sと変わらない仕様になっています。(パート事の音の効果の調整はひと手間増えるイメージです)
TRシリーズはHIP-HOPやクラブミュージックに欠かせない音色で、各社が似せた音(あるいは録音ベースで再現)を展開している中、本物の音をモデリングで再現した現代のTRです!
見た目が人を選びそうですが、抜群の操作性で大活躍間違いなしなデジタルモデリングシンセサイザーで、神機材です!
★ミドルグレードおすすめ:Korg「drumlogue」
僕も愛用するリズムマシンです!
現在ミドルグレードといえるようなリズムマシンは上述の「TR-6s」とこの「drumlogue」くらいしか無いのですが、機能的にはこの「drumlogue」の競合は「TR-8s」になってきます。
最大の特徴として、こちらはバスドラム、スネア、タム、ハイハットがアナログシンセサイザー、それ以外がデジタルシンセサイザーになっているハイブリッドシンセサイザーです。
TR-sシリーズと同じく、デジタル部分でリズム帯以外のウワモノも流せてしまう優れものです。
音はTRシリーズと比較すると硬派な印象ですが、存在感と洗練された印象のいい音がきっちり鳴る隠れた名機だと僕は思っています!
「TR-8s」ほどには操作性が即興には向かない(リズムマシンとしての操作性はきっちりあると僕は感じています)、個体が黒一色でいまいち映えないせいか不人気機種のようですが、その分少し価格が落ちて、機能と価格っが釣り合っていない絶好の状態になっています!
Korgらしく、メタルボディ、サイドウッドパネルの本格的な質感の個体なので、愛着を持ちやすいおすすめのリズムマシンです。

★エントリーグレードおすすめ:Korg「VOLCA」シリーズ(VOLKA BEATS)
リズムマシンは2万円台~のエントリーグレードも比較的いい機材が多くあり、中でもRolandのT-8やBehringarのTBシリーズ等おすすめ機種が複数ある中で、あえてコスパ最強格のKorg「VOLCA」シリーズです。
このVOLCA BEATSはアナログリズムマシンで、使いやすいサイズ、電池駆動可能と、シンプルで迷いにくい操作性を評価しています!
上記で触れましたが、RolandのTRシリーズはあまりに有名なので、BehringarのTBシリーズ(TRクローン)だけでなく、プラグインシンセサイザーでも近しい音が使えたりするので、アナログの非Rolandの唯一性と最強コスパでおすすめとして掲載しています!
★番外編おすすめ:elektron「Digitakt」
厳密にはサンプラーの方が正しいですが、きっちりシンセサイザーとして音色を作りこめるリズムマシンです。
サンプル音源をとにかくいじり倒して、全く別物とまで呼べる音まで変化させてリズムに組み込む使い方が評判が良いです。
操作性は独特な印象がありますが、リズムマシンの情報を調べると必ずこの機種が登場するくらいに評価が高い機材です!
Rolandの音はすでに満足してるよ!なちょっと初心者ではない方にはお勧めできる機材と思います!
★セミモジュラーシンセサイザーについて

出典:AMAZON
セミモジュラーシンセサイザーは後述するモジュラーシンセサイザーの音を鳴らす機能を最低限積み込み、モジュラーシンセサイザーの様に複数のパーツをコードでパッチングしなくても、単体でもモジュラーシステムでも活躍できるようにしたシンセサイザーです。
それぞれモノフォニックだったり、ポリフォニックだったり機種によって音数にバリエーションがありますが、ここではセミモジュラーシンセザイザーとして一括りで扱います。
モジュラーシンセサイザーと同様、個々の音響モジュールをコードでパッチングし、より音の作成の自由度を上げています。
(そもそも論でいくと、モジュラーシンセサイザーがシンセサイザーの原点だったりします)
単独で鍵盤がついていないものが多く、別途シーケンサーが無いと「プー」といった連続音のみ出す個体もあったりして、深いです!
プリセットも無いものが多く、玄人向きですが、独自性を突き詰めるとこのシンセイサイザーの分類にたどり着くと思います!
演奏でもDTMでも何か一味つけたいとき重宝するのがモジュラー及びセミモジュラーシンセサイザーです!
こちらもデジタルシンセサイザーが極少数ありますが、ほぼアナログシンセサイザーです!
★ハイグレードおすすめ:MOOG「Grandmother」
アナログシンセサイザーの原点、MOOGの鍵盤付きセミモジュラーシンセサイザーです!
「Mother-32」や「Subharmonicon」等MOOGにはイケてるセミモジュラーシンセサイザーが他にもありますが、
この機種はデミモジュラーシンセ特有の自由度、伝統のMOOGサウンド、単体での演奏の楽しさを詰め込んだモノフォニックアナログシンセサイザーです。
音として、個体として存在感が極まっているのが当機種の特徴と僕は思います!
★ミドルグレードおすすめ:Behringar「NEUTRON」
シンセサイザーの往年の名機をクローン強化した機材が多いBehringarですが、この「NEUTRON」は完全オリジナル。
ミドルグレードとしていますが、エントリーグレード寄りの価格帯ながら、音の表現の幅が広く、アマチュアからプロまで高評価なセミモジュラーパラフォニックシンセサイザーです。
シーケンサーも鍵盤もついていないので、別途何かに繋がないと演奏や音の調整は難しいですが、モジュラーユーロラックに組み込める規格なので、用途の多様性も幅広いです!
少し玄人よりの機材と感じます!
★ミドルグレードおすすめ:Korg「MS-20 MINI」
上記のMOOG「Grandmother」と同じく、鍵盤付きセミモジュラーシンセサイザーです!
Korgの往年のモノフォニック・シンセサイザー「MS-20」を現代の技術で呼び戻したモノフォニックシンセサイザーです!
色褪せない存在感の音色とそばに置きやすい絶妙なサイズ感、操作しやすい操作部分と、バランスにとにかく優れたデミモジュラーシンセサイザーだと思います!
これぞモジュラーシンセサイザー!というわかりやすい可愛い見た目も高評価!(MS-20まんまです)
★エントリーグレードおすすめ:Beringar「GRIND」
モノフォニックシンセサイザーで紹介した同社の「CRAVE」によく似た機種で、「CRAVE」やMOOGの名機の完全クローン「MODEL D」をここで掲載してもいいのですが、この機種は最初のセミモジュラーシンセとしては最も用途が広いと考えて、採用しています!
この「GRING」はセミモジュラーシンセサイザーでありながら、発振部分はデジタル、フィルターがアナログのハイブリッドモノフォニックシンセサイザーです。
このデジタルオシレーターのおかげで、多彩なサウンドメイクが可能(CRAVEのようなMOOGライクな音色もできる)、パッチングでさらなる変化をつけられる、エントリーグレードの価格帯で個体の質感も「CRAVE」と同様で高評価。
鍵盤こそついていないですが、「CRAVE」と同様にシーケンサー部分のボタンが鍵盤の代用になるので、ちょっとした演奏を単機で楽しめます!
★モジュラーシンセサイザーについて

出典:AMAZON
モジュラーシンセサイザーはシンセサイザーの原点で、各モジュールをパッチングして音を鳴らし、調整する事ができるシンセサイザーです。
ほぼアナログシンセサイザーですが、発振部のオシレーターやフィルター、電源等が独立した別個体だったりするので、どういったシンセサイザーでどのような演奏で、どんな楽器にするのか、まさしく「自由」です!
ユーロラックと言われる規格箱に各機材を入れて、パッチングケーブルで繋いで一つの楽器とするのが主流ですが、いわゆるアンビエントやノイズミュージックというジャンルのほぼ完全に演奏向きのシンセサイザーになります!
マシンライブで操作演奏していたら間違いなくCOOLな機材ですが、演奏技術と機材投資をかなり覚悟を持たないと手を出しにくい領域でもあります。(だからこそ懐深く、醍醐味に満ちていいるとも思います)
機材も各部位多彩に存在、極論DIYの世界まで到達するので、ここではおすすめ機材は割愛します!
★まとめ!

出典:AMAZON(YAMAHA MONTAGEシリーズのワークステーションシンセサイザー)
以上がDTMを楽しむ身であり、シンセ弾きとして演奏も楽しんで遊んでいる僕自身の視点から厳選した商品を種類別かつグレード別にご紹介しました!
他にもRoland「sp-404 mk2」、AKAI「MPC」、NI社「MACHINE」シリーズのサンプラーと呼ばれるジャンル、Roland「MC-707」といったグルーブボックスと呼ばれるジャンル、SEQUENTIAL(Dave Smith Instruments)社の各種シンセサイザー等まだまだ名機が、ご紹介した機材以外にもいっぱいあります!
適時当記事をリライトしながら、網羅性を高める予定です。
最高に愛着を持てる機材で、相棒が生まれれば、音楽へのモチベーションも爆上がりです。
少なくとも僕はQOLが爆上がりしたと感じています!
少し偏見に満ちた熱量高めの長文紹介記事になりましたが、読者様にとっての使用用途や好みに合っているかどうかの判断材料になれば嬉しいです!
ではまたっ!